「ブラインドの隙間にある日々」
一部
目を覚ますと、窓のブラインドの隙間に三本の線が走っていた。
一本は電線の影、一本はビルの角の影、もう一本はどこから来たものか分からない。
三本は揺れもせず、ただそこにあった。
ベッドから足を下ろす。床は冷たく、その冷たさは昨日と変わらなかった。
変わらないという事実は、無味の飴を口に含んでいるみたいに、薄く広がる。
時計は七時を少し過ぎている。冷蔵庫は同じ音を出し、隣の部屋のテレビはニュースを流している。
内容は聞き取れないが、アナウンサーが笑っていることは分かる。
笑い声らしき響きが部屋の空気に混じって、水っぽく膨らむ。
流し台に置きっぱなしのカップをゆすぎ、コーヒーを淹れる。
湯気が立ち上がり、ブラインドの線を霞ませる。
外では出勤する人の靴音が交差し、通り過ぎていく。
コーヒーを飲みながら、壁の小さな欠けを数える。
数はいつも同じはずなのに、数え直すうちに分からなくなる。
終わらないのは数字のせいじゃなく、僕のほうの問題だ。
二部
観葉植物の鉢に指を差し入れると、土は乾いている。
ペットボトルの蓋で三杯、水をやる。
受け皿に少したまった水をティッシュで拭き取り、丸めてゴミ箱に投げる。
外れたので拾って、もう一度投げる。今度は入る。
小さな達成感。朝にはそれで十分だ。
やることリストに「歯を磨く」と書き、すぐ横にチェックをつける。
「コーヒーを飲む」と書き、チェックをつける。
「植物に水」と書き、またチェックをつける。
チェックマークの形は毎日少しずつ違う。
その違いに、わずかな安心を覚える。
午前中はパソコンの前に座る。
受信箱には重要そうで重要でないメールが溜まり、重要でなさそうで重要でないメールも溜まる。
どちらにしても溜まる。
いくつか開いて閉じる。返事は書かない。
書いたつもりになり、書かなかったことを忘れる。
忘れる前に、忘れたような感覚が胸に広がる。
それは軽いめまいみたいなものだ。
三部
十一時ごろ、廊下に宅配便の足音がする。
僕の部屋の前では止まらず、代わりにポストに紙が落ちる音がした。
拾い上げると、301号室宛の封筒だった。
しばらく親指と人差し指で挟んだまま、糊の線を見ていた。
封を切りたいほどの好奇心はない。
切らないでいられるほどの意志もない。
どちらでもないので、廊下に出て301号室の前に置き、
少し離れて白い封筒を眺めた。それで終わりだ。
廊下には昼の匂いが漂っていた。
カレーの匂い、洗剤の匂い、古い木の匂い。
それらが無理なく混じり合っている。
四部
午後、光が傾き、ブラインドの縞が本棚を横切る。
背表紙に影がかかり、知らない作家の名前が知っている誰かの名前のように見える。
読んでいないページが、読んだページより多い。
多いことは悪くない。
スマートフォンを開くと、おすすめの記事が並ぶ。
街の夕焼け、どこかの限定メニュー、終わったセールの広告。
スクロールを途中でやめる。やめたことだけが手に残る。
夕方、部屋の色が減っていく。
照明のスイッチは押せる高さにあるが、押さない。
外の看板の光が壁に四角い湖を作る。
青いようで青くない、白いようで白くない。
五部
夜になると、向かいのビルの窓に赤いカーテンが見えた。
昨日は気づかなかった。
カーテンの向こうに誰かがいるのかもしれない。いないのかもしれない。
ガラスに自分の顔が映り、それは僕のようで僕ではない。
指でなぞる真似をしてみる。ガラスには触れない。
触れないことで、ガラスはガラスであり続ける。
冷蔵庫を開けて閉める。
昨日と同じものが同じ位置にある。
違うのは光の角度と僕の視線の高さ。
床に寝転び、天井を見上げる。
小さな点を結んでも、どこにも行かない線ができる。
電話は鳴らない。今日は鳴らなかった。昨日はどうだったか、思い出せない。
眠る前に、観葉植物の葉が一枚落ちた。
音はしなかった。拾って本の間に挟む。
平らになることが叶うこととは限らない。
けれど、この部屋では、そういうことになっている。
翌朝、また目を覚ます。
ブラインドの隙間の線は二本になっていた。
理由は分からない。分からなくても、二本は二本だ。
冷蔵庫はまた音を立て、やがて止まり、また始まる。
ブラインドの線は揺れず、そこにある。
僕はコーヒーを飲む。
飲み込まれたものは形を失い、失っても何も失われない。
そうして一日が過ぎ、一日になる前の一日がまたやってくる。
終わらない前に、終わっている。
終わったあとに、終わらないふりをしている。
ここはそういう場所だ。
僕はその中に立っている。
立っているだけで、十分だ。



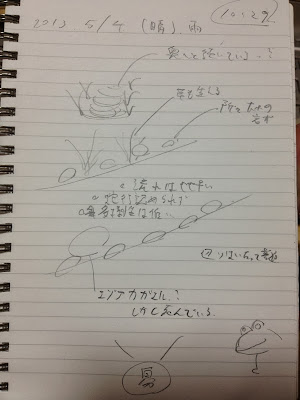
コメント
コメントを投稿